| |
|
| 1720 |


●アスニー山科 山アスギャラリーで「ふるさとの会パネル展」を開催中(9/2~9/30)
ふるさとの会では、恒例になりました「ふるさとの会パネル展」を、アスニー山科 山アスギャラリーをお借りして、
9月2日から9月30日までの約1ヶ月間行っています。
今回は11月10日(日)に実施予定の「ふるさと山科再発見 第7回山科の遺跡・遺産巡り」で訪れる予定の中臣遺跡について、
A3判パネル44枚で紹介しています。
アスニー山科にお越しの節は、ぜひご覧下さい。
|
| 1719 |


●「第6回 ふるさと講演会」は、台風10号接近のため、10月26日(土)に延期します。
ふるさと講演会 ご参加予定のみなさまへ
8月31日(土)に予定しておりました「ふるさと講演会」ですが、8月30日~31日にかけて、台風10号が接近し、その影響で近畿地方は風雨が強くなることが予報されておりますので、大事をとりまして安全第一を考え、
8月31日(土)の「ふるさと講演会」を 中止 とし、10月26日(土)に 延期 する こととなりました。
ご参加を予定してしていただいていた皆さまには、大変ご迷惑をおかけしますが、よろしくご協力のほどをお願い申し上げます。
2024.8.28.11:30 ふるさとの会事務局
第6回ふるさと講演会
日時 令和6年(2024)10月26日(土)13:30~16:00(受付13:00より)
会場 本願寺山科別院(西御坊)多目的ホール
演題 「山科“小山地域”の伝統行事と原風景を語る」
講師 竹谷 武雄 氏(小山地域、“二ノ講”保存会会長)
申込 事前申込みは不要です。定員 70名(先着順)
参加費 500円(会場費・資料代)
|
| 1718 |


●小金塚第1町内会の地蔵盆
8月24日(土)、「地蔵盆調査」のために、四ノ宮小金塚地域の地蔵盆にお伺いしました。
小金塚は、「小金塚自治連合会」の発足した昭和40年頃から、今日まで地蔵盆を行っています。
初めは、小金塚全体で行っていましたが、あまりにも子どもの数が増えたため、30年ほど前から4つの町内に分かれ、最近では6つの町内に分かれて地蔵盆が開催されています。コロナ禍の中でも内容を縮小しながら続けてきたそうです。
この日は、小金塚第1町内会、同第2町内会、同第3町内会、同第4町内会の4カ所で地蔵盆が開催されていました。
第一町内の地蔵盆は、路上や屋内外ガレージを使い行われていました。午前11時から「ラジオ体操」で始まり、夜9時まで行われます。
町内会主催で、参加者は、約130名(大人90名、子ども40名)と、大変賑やかです。
行事は、おやつ配布・福引(子ども)・福引(大人)・ふご降ろし・ゲーム(子ども)で、「夜店」もあります。祀られているかわいいお地蔵さんは、化粧されお供えもありました。
この町内では、「福引き」の中で「ふご降ろし」が恒例として行われています。ハラハラドキドキしながら、子ども達が景品を待っている姿が印象的でした。
この夏の地蔵盆調査の結果は、調査に参加した会員の調査結果をまとめて、またご報告させていただきたいと思っています。
|
| 1717 |


●四ノ宮「六地蔵巡り」の調査
「六地蔵めぐり(ろくじぞうめぐり)」とは、毎年8月22日と23日の両日に、京都の旧街道口に安置された6体の地蔵尊を巡拝するもので、800年も続いている伝統行事です
。
各箇所で授与される赤・青・黄・緑・自の色とりどりの「お幟(おはた)」を束ねて護符とし、家の玄関に吊すと一年の疫病退散・無病息災・家内安全、福徳招来の御利益があるといいます。
ふるさとの会では8月22日(木)夕方に、旧三条街道の山科交差点から四ノ宮交差点まで歩いて、四ノ宮「六地蔵巡り」の調査を行いました。これはコロナ禍を経て、以前と以後でどのような変化があるのかを調べるためです。
当日は、夕刻になり少しは涼しいかと思いましたが、良い天気で、まだ明るかったせいか、日中に負けない位の「猛暑」の中での調査となりました。
夕暮れまでには少し時間がありましたので、子ども達もたくさん来ていました。三条通りは、たいへんにぎやかで、屋台のお店も繁盛していました。ただ屋台のお店の数自身は、コロナ前の最盛期に比べると3分の2程度に減っているようでした。
今後、調査に参加した会員の結果や意見をまとめて、またご報告させていただきたいと思います。
|
| 1716 |


●8月17日(土)~8月25日(日)、山科各地で行われている「地蔵盆」の調査をしています。
山科の夏の風物詩である「地蔵盆」
10年ほど前に、ふるさとの会では山科各地の「地蔵盆」の悉皆調査を行いました。
ふるさとの会が2014年に調査したところによれば、
区内263カ所で開催され、子どもが9,699名、大人が12,647名、合計で22,346名が参加する山科最大の伝統行事の一つとなっていることがわかりました。
しかし、「コロナ禍」を経て、地蔵盆の中止や、縮小の声などもよくききます。
実際のところ、山科の「地蔵盆」は、今、どのように実施されているのか、また変わってきているのか。
そうしたことを念頭に、今年度から、地蔵盆の再調査に取り組んでいます。
結果については、ふるさとの会でまとめを行い、その特徴などについて、山科区民のみなさんにも情報を発信し、還元していきたいと思います。
またみなさんの所に調査員がお伺いしましたら、ご協力をよろしくお願いいたします。
(写真は小野学区内で行われた地蔵盆で、僧侶が読経されているようす。許可を得て撮影させていただきました)
|
| 1715 |

 
●8月3日(土)「山科夜市」に「子どもコーナー」出店 多くの子ども達が来てくれました。
2024年8月3日(土)に、山科商店会主催の「山科夜市」(1日目)が開催され、ふるさとの会も協力、「子どもコーナー」を出店しました。
開催時間は午後5時からですが、スタッフは午後4時に集合。テントを立てたり、オリジナル「色紙風車」の見本をつくったりして準備をしました。
この日は、当初の天気予報では午後3時に40℃になるとの予想。実際には40℃までは上がりませんでしたが、それでも「酷暑」と言える日でした。
午後4時でも、まだかなり暑い時間帯でした。
午後5時から開店、続々と子ども達が来てくれました。
いっしょに「風車」つくりをします。簡単につくれて、少しの風でもよくまわる風車です。
カラフルな色紙の色が映えます。
材料はたくさん用意したのですが、どんどんと子ども達がやってきてくれて、
午後7時30頃には、風車の材料が無くなってしまい。やむなく早めの閉店となりました。
次の日、8月4日(日)の2日目には、たくさん材料を用意して、前日と同様にお店の開店準備をしましたが、
準備ができた頃から、激しい雷雨に見舞われ、「大雨警報」も発令されたため、
残念ながらこの日は「ふるさとの会ブース」を中止としました。
楽しみにしていた子ども達には、申し訳ないことでしたが、仕方がありません。
スタッフのみなさん、ごくろうさまでした。
|
| 1714 |


●8月1日(木)京都橘大学歴史遺産学科との合同石造物調査(2)(光照寺墓地)
2024年8月1日(木)に、先の7月25日に続き、第2回目の合同調査を行いました。
今回は、東野北井ノ上町にある「光照寺墓地」を調査しました。大学側からは学生さん5名を含む7名の方の参加がありました。
ふるさとの会の調査では、この光照寺墓地にある戦没者の墓標は19基ありました。
この中で、満州事変や日中戦争など昭和16年(1941)の日米開戦までに亡くなった方の墓標は3基、開戦後に亡くなった方の墓標は15基でした(不明1基)。
また亡くなった方の年齢は、10代1名、20代前半2名、20代後半3名、30代前半2名、30代後半3名となっています(不明8名)。
亡くなった場所は、国内3名、中国大陸2名、フィリピン6名(レイテ・ルソン・マニラ・バタン・他)、その他の海外地域6名(インド・ビルマ・ニューギニア・南洋諸島・他)でした(不明2名)。
また、海軍所属が8名で陸軍が11名。この海軍所属者の墓碑は、山科の中ではこの光照寺墓地が最も多く。音羽地域の若者たちは海軍に多く徴兵されたことが伺えます。
昭和5年(1930)9月に京都府山科町役場が発行した『京都府山科町誌』には、第3編「兵事」の項で「西南の役」以降の従軍者や殉難者、戦傷者などが記録として残されていますが、
むろん昭和6年(1931)の満州事変を始めそれ以降、昭和20年(1945)終戦までの記録は記載されていません。
また、山科における戦没者たちのきちんと整理された記録も見たことがありませんので、
地元の若者たちが、あの大戦で戦地に赴き異郷の地に没していった記憶を、きちんと記録として残して未来に伝えて行くことは、
大変重要な事業であると考えています。
なお、この日の調査の様子は、同日のNHKテレビ18:45からの「京いちにち」番組の中で放映されました。
|
| 1713 |

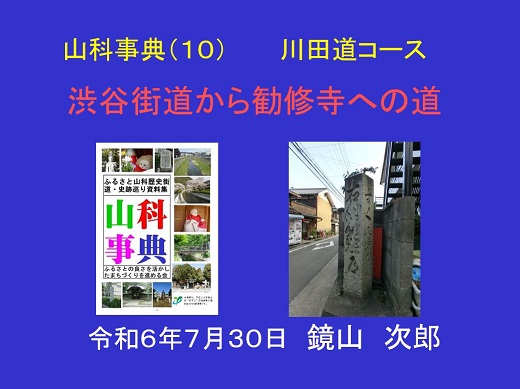
●7月30日(火)山科歴史学習会(御陵団地集会所)
ふるさとの会の「山科歴史学習会」(部会)では、2024年7月30日(火)に『山科事典』をテキストに「川田道コース」の勉強会をしました。
この「山科歴史学習会」では、「山科の歴史を系統的に学習しよう」と部会を立ち上げ取り組んでいるもので、
現在までに『山科町誌』『史料京都の歴史11山科区』『禁裏御家人 山科郷士 起承転結』『山科郷史』『山科の歴史と現代』などをテキストに学んできました。
その後、新しい部員も増えてきましたので、現在は、ふるさとの会作成の「山科歴史街道資料集 山科事典」をテキストに、
毎回、1コースづつを学んでいます。
現在迄に
1 旧東海道・西コース
2 旧東海道・東コース
3 山科川コース
4 西野道コース
5 山科疏水・西コース
6 山科疏水・東コース
7 妙見道コース
8 大岩街道コース
9 旧渋谷街道コース・渋谷街道コース
を学んできました。7月30日(火)の勉強会は、第10回目となり「川田道コース」を勉強しました。
学習会では、始めに約1時間ほど、鏡山次郎氏から、内容の説明があり、後半約1時間は参加者からの質問、追加説明などで深めています。
今回は、川田道沿いにある、花山稲荷神社・折上稲荷神社・中臣(稲荷)神社など由緒が、
延喜3年(903)の醍醐天皇の行幸と関わりのあることや、その時に醍醐天皇が詠まれたと伝わる和歌などに関して議論が盛り上がりました。
話を聞いているだけでも、山科を深く理解する上で勉強になる会ですので、
興味・関心のある方は、ぜひご参加いただければと思います。
(注:ふるさとの会の会則では「部会は会員を持って組織する」となっていますので、学習会参加には、ふるさとの会の会員になっていただく必要があります)
|
| 1712 |


●7月27日(土)勧修学区夏まつり(勧修小グランド)
2024年7月27日(土)、毎年恒例の「勧修夏まつり」に、ふるさとの会もパネル展示や子どもコーナーで参加しました。
「勧修夏まつり」は、勧修おやじの会が主催し、第16回目となります。ふるさとの会も毎回参加をさせていただいています。
この日も暑い中でしたが、午後4時から準備をはじめ、
南校舎運動場側に「勧修小学校150年のあゆみ」「ふるさとの会の遺跡・遺産巡り紹介」などパネル80枚を展示しました。
そしてこれも、毎年好評の子どもコーナー「折り紙風車」を子ども達と共に作成しました。
230組の材料を準備しましたが、子ども達がひっきりなしにやって来てくれて、大盛況でした。
子ども達が喜んでくれる姿がみられることは、同時に私たちの喜びでもあります。
テントや机・イスなどは、勧修おやじの会から提供していただき、大変ありがたかったです。
御参加されたスタッフのみなさん、ありがとうございました。
|
| 1711 |


●7月25日(木)京都橘大学歴史遺産学科との合同石造物調査(1)(小山共同墓地)
2024年7月25日(木)午前10時から12時まで、小山共同墓地の調査を、ふるさとの会と京都橘大学歴史遺産学科の学生さんたちと合同調査を行いました。
これは第16年次(2023年度)から合同で行っている「石造物調査」(3D化して記録に残す)の一環として行ったものです。
当日は、ふるさとの会から8名、大学側から3名が参加し、「戦没者墓碑」を中心に、調査や撮影を行いました。
ふるさとの会では10年前の2014年10月にも「山科の戦没者墓標」調査を行い、区内30カ所の墓地を調査して、約270基の墓碑があることを確認しています。
今回は、10年を経てどのような変化があるのか調べるということも一つの課題でした。
また、前回の調査では、古い石造物のため読めなかった文字なども、3D化作業の中で解読が進み、新たなことが解ってきたのも大きな成果でした。
当日は、猛暑の中で下が、熱中症対策をとりながら調査を進めることができました。
この種の調査は、今後とも継続して行っていく予定です。
|
|
 |
 |
これ以前(17年次の1)は、こちらをごらん下さい。(1701~1710) |
 |
これ以前(16年次の5)は、こちらをごらん下さい。(1640~1650) |
 |
これ以前(16年次の4)は、こちらをごらん下さい。(1630~1640) |
 |
これ以前(16年次の3)は、こちらをごらん下さい。(1620~1630) |
 |
これ以前(16年次の2)は、こちらをごらん下さい。(1610~1620) |
 |
これ以前(16年次の1)は、こちらをごらん下さい。(1601~1610) |
 |
これ以前(12年次の5)は、こちらをごらん下さい。(1240~1244) |
 |
これ以前(12年次の4)は、こちらをごらん下さい。(1231~1240) |
 |
これ以前(12年次の3)は、こちらをごらん下さい。(1221~1230) |
 |
これ以前(12年次の2)は、こちらをごらん下さい。(1211~1220) |
 |
これ以前(12年次の1)は、こちらをごらん下さい。(1201~1210) |
 |
これ以前(11年次の10)は、こちらをごらん下さい。(1191~1200) |
 |
これ以前(11年次の9)は、こちらをごらん下さい。(1181~1190) |
 |
これ以前(11年次の8)は、こちらをごらん下さい。(1171~1180) |
 |
これ以前(11年次の7)は、こちらをごらん下さい。(1161~1170) |
 |
これ以前(11年次の6)は、こちらをごらん下さい。(1151~1160) |
 |
これ以前(11年次の5)は、こちらをごらん下さい。(1141~1150) |
 |
これ以前(11年次の4)は、こちらをごらん下さい。(1131~1140) |
 |
これ以前(11年次の3)は、こちらをごらん下さい。(1121~1130) |
 |
これ以前(11年次の2)は、こちらをごらん下さい。(1111~1120) |
 |
これ以前(11年次の1)は、こちらをごらん下さい。(1101~1110) |
 |
これ以前(10年次の1)は、こちらをごらん下さい。(1001) |
 |
これ以前(8年次の7)はこちらをごらん下さい。(851~868) |
 |
これ以前(8年次の6)はこちらをごらん下さい。(851~860) |
 |
これ以前(8年次の5)はこちらをごらん下さい。(841~850) |
 |
これ以前(8年次の4)はこちらをごらん下さい。(831~840) |
 |
これ以前(8年次の3)はこちらをごらん下さい。(821~830) |
 |
これ以前(8年次の2)はこちらをごらん下さい。(811~820) |
 |
これ以前(8年次の1)はこちらをごらん下さい。(801~810) |
| |
 |
 ふるさとの会の活動
ふるさとの会の活動
