| 鏡山次郎HP |
 ふるさとの会文章部会 山科人 編
ふるさとの会文章部会 山科人 編
(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)
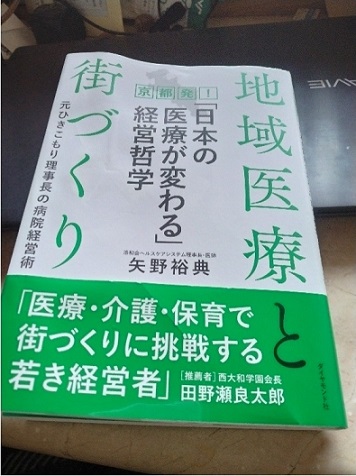
音羽病院と山科
最近こんな本を読んだ。タイトルは長く、
『地域医療と街づくり 京都発! 「日本の医療が変わる」経営哲学 元ひきこもり理事長の病院経営術』
というもので、表紙がほとんど本の題名で占められている。著者は矢野裕典氏である。2022年4月から「洛和会ヘルスケアシステム」理事長である。
文中に出ていたものから経歴を抜き出してみた。
1981年生まれ 下京区「矢野医院」の院長、矢野一郎氏の長男として出生。父、一郎氏は「丸太町病院」も経営し、のちに「音羽病院」も創設した。
「聖ドミニコ学院京都幼稚園」から「ノートルダム学院小学校」そして西大和(三年生を2年)学園中学校・高校卒業、帝京大学医学部卒業後2017年に医師国家試験に合格。ここだけならわからないが、途中で留年が何度もある。
「1 2 333 44 5 66666」 6年制の帝京大学医学部での進級にかかった年数をならべたものである。その大学時代には田野瀬良太郎国会議員(西大和学園創設者、奈良県選出)の事務所でボランティアを続けていたという。2017年春医師国家試験に4回目で合格したが、研修医の途中でリタイア(2017冬)。その後大阪市内の特別養護老人ホームで介護職2018春まで奉職。父親から「帰ってこい」と言われたという。
そして2019年4月から副理事長、2022年4月から理事長に就任している。
病院についてであるが、音羽病院の経営母体はこの洛和会ヘルスケアシステムである。グループ全体の職員6000人以上 京都市内に病院5つ、提携クリニック5を有している。(音羽病院の看護師は600名、医師は常勤187名、ベッド数は548床)
「救急車受け入れ台数年間合計10270台(2022年度 丸太町病院・音羽病院の合計)」という新聞広告が出ていた。京都府内の民間病院では最大と言ってもよいのではないか。
この書の後半で書かれているのが、理事長になってからの改革していった内容である。たとえば「洛和会 福利厚生ガイドブック」によると、職員が「結婚するとき」の項目では、
対象者
①事実婚にある者
②同性パートナーを有する者
と明記されている。なかなか進歩的な取り組みであると言える。
また、VHJ(全国の民間病院のネットワーク)により地域医療の「経営」と「質」の向上をはかる、として共同購入により割安で医療品や医療機器を購入可にしたり、よく話題になる災害派遣医療チーム「DⅯAT」の活躍もしたりと意欲的だ。新型コロナウィルス禍の時を乗り越えたのも記憶に新しい。山科以外からの受け入れも多かったようだ。
さて音羽病院が開院したのは1980(昭和55)年である。それまで同地で「山科観光ホテル」が昭和43年ごろから昭和45年ごろまで営業していたことが『山科検定参考資料集』(令和6年10月山科検定委員会発行)にも出ている。万博目当てのホテル建設のラッシュがあった時代である。(ちなみに山科では同じく営業不振で廃業したが「京都オリエンタルホテル」も同時期であった)名神インターチェンジにも近くさぞ観光客が多いことを見込んでいたのであろう。ともかく倒産したホテル跡を買い取って病院にしたようだ。
さて、これからは読後の辛めの批評である。山科に住むわれわれにとっては365日24時間、総合病院が近くにあることはありがたいことである。そんな頼りになる病院が地域にどんな貢献をして、しかも街づくりに取り組もうとしているのかが正直この本からは見えてこない。「引きこもり」の少年期を過ごしてそれによって得たものが、どのように病院経営や地域にいかされるのかがよくわからなかった。「自分にはリーダーシップがある」とたびたび文中に出てくるが、進学一辺倒の高校で生徒会長をしたことがそんなにリーダーシップを発揮したことにはならないと思う。みんなの信頼を得て学校と渡り合って校則を変えた、というところまではいってないのだが、どうだろうか。
話題は変わるが、まもなく89歳を迎える義母はデイサービスに出かけるときに「今日はあんまりうれしくない」と家人にもらす時があるという。世話をしてくれるスタッフが優しくない日だから、と言うのだそうだ。日常的にわがままな年寄りと接する家族にとって、元気よく迎えの車に乗ってくれるときほどありがたいことはない。
知人で熱心に老人ホームを何か所も見学して回っていた人がいた。しっかり調べて決めたけれど、入所してしばらくして担当や施設長が交代したら、とたんに入所者に対する態度が変わって居心地が悪くなった、などという話であった。
病院が設備や経営面でのハードな部分を追及して評判を得るよりも、入院患者が日々接する看護師や職員がどれだけソフトな対応をしてくれるかが大切だ。理事長がそこまで入っていけるかが病院の評価の分かれ目になるはずだ。落ちこぼれた少年が医者をあきらめ、病院の経営を成功させた、という成功譚では今一つ満足感が得られない。文章で表現するトレーニングが筆者には不足しているように見える。
厳しい批判をするが、逆に期待も抱いている。地元の病院が今後どれほど地域に寄り添ってくれるかでまさしく山科が「良い街」になる可能性がある。本には出ていなかったが、「農福連携」で病院が農業に関わっていけるか、ということで理事長が近くの農家を訪ねたということだ。おもしろいところに目を向けたものだと思う。この面で突破口が開くかもしれない。今後注視していきたい。
(山科人 2025年2月25日)
*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)