| 鏡山次郎HP |
 ふるさとの会文章部会 寅次郎 編
ふるさとの会文章部会 寅次郎 編
(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)
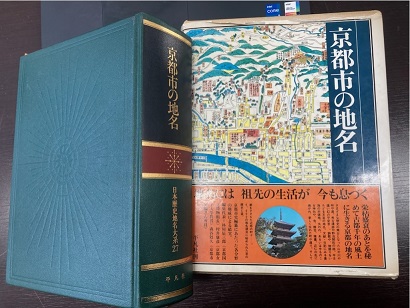
意味は生み出される!
前回の私のコラムでは、「記号接地問題」を取り上げた。記号接地というのは、ある言葉とその言葉が指し示す意味が対応していることを理解できている状態をいう。
例えば、「山科」という言葉は、京都盆地からみて東側にある山科地域を意味していることを理解できている場合は、記号接地しているということになる。
しかし、私は、ここで次のような疑問を感じてしまう。
“京都盆地の東側にある山科地域は、いつから山科になったのだろうか?”
鏡山次郎氏のホームページの「山科地名物語」には、次のような記述がある。
| 山科の名が歴史上はじめて登場するのは669年(天智天皇8年)5月5日のことで、日本書紀に「天皇(天智)、山科野に縦猟(かり)したまふ。」と書かれているのが最初だが、扶桑略記に「天皇(天智)、馬を駕し山階(やましな)郷に幸ず。」と書かれているように、古くは「山階(やましな)」と書かれることが多かったという。「シナ」というのは、もともと坂道・階段・階層という意味の音(オン)で、漢字は「品・科・階」などがあてられた。山からなだらかな斜面となって盆地を形成している地形からつけられた名前であると言われている。ちなみに、日本で山科という地名がつけられているのは「京都市山科区」と、明治のはじめ山科郷士が開拓をした「東山科村」(現在の千葉県千葉市緑区東山科町)だけである。 「山科里(やましなのさと)」は歌枕にもなっており、和泉式部の「帰るさをまち心みよかくながらよもただにては山科の里」(後拾遺集19巻)という歌もある。 古くは「山城国山科郷」と呼ばれていたが、1890年(明治22年)の町村制施行で「京都府宇治郡山科村」となり、次に1926年(大正15年)「京都府山科町」、さらに1931年(昭和6年)「京都市東山区山科」となり、1976年(昭和51年)10月に「京都市山科区」として独立した。 |
ここには「山科」という地名の歴史的な変遷が記されており、山科は、天智天皇の時代には存在していたというのが私の疑問に対する答えになるだろう
しかし、私には、さらに次のような疑問が湧いてくる。
“日本書紀に「山科野」という地名が登場する前に「山科」は存在したのだろうか?”
もし、日本書紀より古い史料に「山科」という言葉が登場していることが判明すれば、少なくともそれ以降は山科は存在したといえるかもしれないが、そうでなければ、日本書紀より前には山科は存在していないということになるのではないだろうか?
なぜ私がこんなことにこだわるのかというと、一般的には、ある言葉が生み出される前にも、その言葉に対応する意味や概念は客観的に存在していたはずだと理解されていることが多いと思われるからだ。
例えば、「犬」という言葉に対応する動物は、この言葉が生み出される前から客観的に存在していて、それに名前を付けて「犬」と呼ぶようになったのだという考え方だ。
このことを「山科」に当てはめてみれば、山科という名前が付けられる前にも、この地は、「山からなだらかな斜面となって盆地を形成している地形」という客観的な実体は備わっていたはずであり、その実体に対して「山科」という名前を付けたのだということになる。
キリスト教社会では、この世界は、唯一絶対的な存在である神が創ったと考えられていて、世界に存在する事物の意味(概念)も神が創ったものであって、それに対して名前を付けたのが言葉であるという考え方が中世までは支配的であったと言われている。
しかし、この考え方には重大な欠陥があることを、フェルディナン・ド・ソシュール(1857~1913)というスイスの言語学者が指摘した。
例えば、虹は世界各地で同じように観察される。虹を構成する色の概念(意味)というものが、その色を表現する言葉が生まれる前に客観的な実体として存在しているのであれば、その実体に対する名前として付けられる色の言葉の数(色の数)はどこの国でも同じになるはずだ。しかし、虹の色は、日本では七色の言葉で表現され、フランスでは四色の言葉で表現ざれ、アフリカのある国では三色の言葉で表現される。
また、日本では「水」と「お湯」という言葉があるが、英語ではどちらも「ウォーター」という言葉で表現される。言葉が生まれる前に客観的な概念(意味)が存在するというのであれば、このような違いは生じないはずだ。
「山科」について言えば、「山からなだらかな斜面となって盆地を形成している地形」は日本全国にたくさんあると思われるが、同じ地形をしていても、京都の山科以外の地(千葉県の東山科町の地形を私は知らないのでここには含めない)は、別の名前で呼ばれていると考えられる。もし、「山科」という言葉が生まれる前に「山からなだらかな斜面となって盆地を形成している地形」が山科を意味していたというのであれば、全国に山科という地名がたくさん存在するはずだが、そういう事実はない。
このような事例は調べればいくらでもあると言われている。
このような事実を踏まえ、ソシュールは、従来の言語観を根本的にひっくり返すような以下の言語論を展開した。
それは、ある言葉が生み出される前には、その言葉に対応する意味(概念)は存在しておらず、その言葉が生み出されると同時にその言葉の意味(概念)も生み出されるのだというものだ。先ほどの山科の事例で言えば、「山科」という言葉が生み出されると同時に「山科の意味(概念)」も生み出されたのだということになる。現代社会においても、「スマートフォン」など昔は存在しなかった新しい言葉が次々に生み出され、それと同時に新しい概念がたくさん生み出されている事実に鑑みれば、ソシュールの考え方は事実に適合しているといえるだろう。
ソシュール以降、現代に至る過程において、ある言葉とその言葉が指し示す意味との関係についての考え方は、ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタイン(1889~1951)というオーストリア出身の言語哲学者の登場によって、さらに劇的な展開を見ることになる。
ヴィトゲンシュタインは、「言語の意味とは言語の使用である」という有名なテーゼを打ち出した。ソシュールが言うように、ある言葉が新たに生み出されることによって、その言葉に対応する意味(概念)が新しく生み出されることは間違いないだろうが、両者の関係は固定的なものではなく、言葉の使用の仕方によって、その言葉に対応する意味(概念)はどんどん変化していくというのがヴィトゲンシュタインの考え方だ。つまり、その言葉がどんな使われ方をしているのかを観察することによって初めて言葉の意味が決まるのだというのである。
例えば、犬という言葉は、一般的には犬という動物を意味するが、「あいつは敵方の犬だ」という使われ方をすると、「犬=スパイ」という意味になる。
以上のようなある言葉と言葉が指し示す意味との関係の話に私がこだわるのには理由がある。
それは、私の愛読書である『京都市の地名(京都市歴史地名体系27)』(平凡社刊、以下『京都市の地名』という)に関係している。この本は、1979年9月20日に初版第一冊が発行され、当時の歴史学、考古学、民俗学、地理学などの分野の著名な研究者が編集委員となって、当時の最新の研究成果を基に編集されたものである。『京都市の地名』は、京都市全体の地理・歴史の記述と併せて、各行政区における地理・歴史、区内の山・川、道、遺跡、社寺。各町名の歴史や由来などについても詳しく記述しており、発刊当時に学術的に知られていた情報はこの本を読めば分かるということで、現在でも歴史学や考古学や地理学などの学者は、この本の内容をベースにしながら研究を行っていると言われている。
私は、東山区長時代に、東山区内の地理や歴史などを調べるときには、まずは『京都市の地名』を読んで基本的な情報を得たうえで、それ以外の情報源にも当たって情報を補足しながら資料を作成していた。
ふるさとの会とのご縁をいただいたことをきっかけに、私は、何気なく『京都市の地名』の山科区の関係の記述を見て驚いてしまった。東山区に関する記述は150頁もの膨大な量があるのに対して、山科区に関する記述はわずか33頁しかなかったのだ。区の面積や人口などを比較すれば、山科区に関する記述の方が東山区よりも多いのではないかと思っていた私は、この事実をどう理解していいのか戸惑ってしまった.
他方で、私は、ふるさとの会の活動に参加するようになって、ふるさとの会や鏡山次郎氏が出版している本を読んだり、それぞれのホームページなどの情報を確認してみて、その情報量の多さにも驚いてしまった。そこには、『京都市の地名』で触れられていない情報がたくさん登場していた。
“これはいったいどういうことなのか?”
確実に言えることは、『京都市の地名』が発刊された1979年時点で当時の歴史学者や地理学者などが把握していた山科に関する情報にはなかった新しい情報がふるさとの会や鏡山次郎氏の著書やホームページにはたくさん搭載されているということだ。このことを、ソシュールの考え方に従って言い換えれば、『京都市の地名』が発刊された時点では存在しなかった山科に関する意味や概念が、新しい言葉と共にたくさん生み出されたということになるのではないだろうか。少し補足すると、『京都市の地名』が発刊される以前にも、山科における様々な歴史的事実は数多く存在していたはずだが、それらの多くは人に知られることなく眠った状態になっていたのを、ふるさとの会や鏡山次郎氏がその事実を掘り起こして新たに言葉にしたことによって、それらの歴史的事実が新たな意味を与えられたことになるのではないかということだ。
例えば、ふるさとの会が今年の4月26日に実施する「第8回 山科の遺跡遺産巡り」で訪ねる「小山の石切丁場跡」については、『京都市の地名』にはまったく記述がない。また、巨大な矢穴痕がある「大名岩」をご神体とする小山の白石神社についても、『京都市の地名』では「白石神社」という名前が紹介されているだけであり、詳しい情報はまったく書かれていない。安土桃山時代にも行者ケ森は、巨石の産地として知られていたようだが、「四つ目の刻印」がある「大名岩」が実際に発見されたのは昭和50年代であると言われている。小山の「石切丁場」や「大名岩」という言葉はその後に生み出され、それと共に新しい意味も生み出されたと言うべきであろうと私は考えている。
また、言葉の使い方によって新たな意味が生み出される事例としては、鏡山次郎氏が、山科を「交通の要衝」と呼んでいることが挙げられるのではないかと私は考えている。
鏡山次郎のホームページ「鏡山次郎 やましな 温故知新」から抜粋すると以下のような記述がある。
| 198 山科は古くから「交通の要衝」と呼ばれていただけあって、古道が多い。多くの歴史を秘めた街道である。そして、今もなお、そうした旅人のための「道標」も多く残されている。 |
| 302 このように大宅は古代から近世に至るまで街道の要衝の地であった。中世には「馬借(ばしゃく)の宿(しゅく)」も置かれていたという。馬借というのは、物資輸送に関わる者で、近江の米や地域の余剰生産物などを運んだ。交通の要衝にあたる大宅村の農民も馬借に参加したと考えられ、江戸時代には農業の合間に大津宿まで出向き、「山科郷中牛馬大津宿日役相勤、七分三分の割合にて商人諸荷物運送仕候」(注3)と、牛馬を使って諸荷物運送に携わった記録も残っている。 |
また、鏡山次郎氏は、2023年5月20日に放送された「ブラタモリ」では、「京都・山科〜要衝・山科は何を生んだ?〜」と題し、「今回の舞台は山科。京都と東日本をつなぐ要衝だからこそ生まれた数々のすごいもの」として、「逢坂関」、「山科本願寺」、「東海道の車石」、「日本初の“山越え”鉄道誕生秘話」などを紹介している。
『京都市の地名』の山科の説明の中では、東海道や奈良街道や逢坂の関の往来のことなどの記述はあるが、私が探した限りでは「交通の要衝」という言葉は見当たらなかった。山科が「交通の要衝」であるという表現は昔からあったようだが、鏡山次郎氏は、改めて「交通の要衝としての山科」という言葉を使うことによって、単に人や物が頻繁に通過していく場所としての山科を意味するだけでなく、京都と東日本をつなぐ極めて重要な位置にある山科において、古代から現代に至るまで、上記の例のような山科ならではの様々な歴史的事実が数多く存在したことを明らかにしている。つまり、山科が「交通の要衝」であるという言葉を使うことによって、それまでになかった山科の新しい意味が生み出されたのではないかと私は考えている。
“もし、『京都市の地名』が新たに刊行される機会があれば、ふるさとの会や鏡山次郎氏が生み出した新たな言葉や情報(意味)を基に研究が進められ、1979年当時とは比べものにならないくらいの豊富な内容になるに違いない!”
私は、密かにそんなことを想像している。
(寅次郎 2025.4.22)
*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)