| 鏡山次郎HP |
 ふるさとの会文章部会 なにば 編
ふるさとの会文章部会 なにば 編
(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)
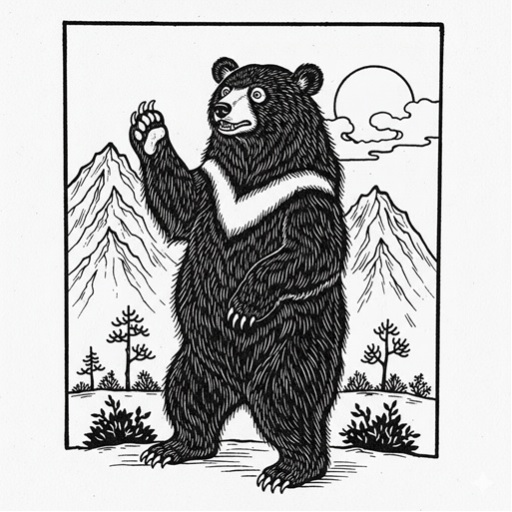
クマの出没
イラストはよく出没するツキノワグマです。Geminiに描いてもらいました。何も言わなくても背景の山や木も描いてくれて、なかなかのものです。
今年は「クマが出た!」というニュースをよく聞きます。私自身はクマに遭遇したことはありませんが、この夏はクマの出没情報があったため、行きたいと思っていた場所へ行けなかったこともあり、ちょっとがっかりしました。でも、安全第一を考えました。
今年は松本と軽井沢を拠点に美ヶ原、鬼押出し園、旧碓井峠、北軽井沢の野鳥の森など涼しいところを求めて森や山を散策しました。しかし、残念だったことがあります。
ひとつは山の上では標高が高いにもかかわらず、暑かったことです。美ヶ原や鬼押出し園は標高が高いため、低木と草しか生えていません。さらに、高山植物の花の季節はもう終わっていました。つまり、あまり見るべき植物がなかったのです。また、高い木がない、つまり、森林ではないので、直射日光を遮るものがありません。その上、空が近いため、日光がじりじりと責めてきます。もちろん、街中と比べれば気温は低めですが、直射日光の威力がすごいので、UVカットの上着や帽子やサングラスが必需品となります。日陰は涼しく、建物の中にいれば問題はないですが、それでは山に行った意味がありません。
美ヶ原は松本側から入り、電波塔の並ぶ王ヶ頭(おうがとう)まで上りました。王ヶ頭は美ヶ原高原の最高地点で標高は2,034mです。山道は石がごろごろしていてちょっと歩きにくく、夜チェックしてみたら、足の裏にマメができていました。電波塔は目印にはなりますが、頂上にある人工的な異物という感じもします。お天気がよかったので、見晴らしがよく、北アルプスの山々がきれいに見えました。美ヶ原はだいぶ昔に来たことがあり、そのときは霧がかかっていて、夏なのに寒かったという記憶があります。今回もその涼しさを求めていたのですが、「標高が高くても直射日光をまともに受けるためじりじりと熱い」というのは大きな誤算というか、私の知識不足でした。
電波塔まで行ったあと、「石ごろごろ道」をすべらないように気をつけて下ってから、「うつくしテラス」で「雲ラテ」を飲み、ゆっくり休憩しました。というと、優雅に聞こえますが、「うつくしテラス」は単なる休憩所で、「雲ラテ」もミルクが泡立っているだけです。紙コップ入りのカフェラテで、ぜんぜんおしゃれな飲み物ではありません。ただ、雑踏を離れて、何もない高原に来たという意味ではリフレッシュできる場所でした。山道を2時間ぐらい歩くと高原美術館にも行けるようですが、今回は時間的な都合で断念しました。
もうひとつの問題は先ほども述べたように、クマの出没です。あちらこちらに「クマに注意」という掲示や看板があり、この先「クマと遭遇して何かが起こっても自己責任だから」と脅されているように感じました。
とにかく、クマには会いたくないと思いました。戸隠に行こうと思っていたのですが、鏡池付近にクマが出るという情報を得たため、長野滞在の予定を変更し、滞在地は松本と軽井沢だけにしました。
鬼押出し園は「クマが出た」ことにより「クマに注意」という掲示だけでなく、奥の院への参道が立ち入り禁止になっていました。奥の院に行きたかったので、とても残念でした。しかたなく、直射日光の攻撃を受けながら奇岩群を眺め、浅間山観音堂までの参道を歩きました。高山植物は時期外れで花が見られませんでしたが、「ひかりごけ」だけはしっかり観察できました。
鬼押出し園には犬を連れた人が結構いました。駐車場近くに「ドッグラン」があり、犬に優しい観光地となっています。犬が奇岩を見て楽しめるかどうか疑問ですが、飼い主は犬といっしょに旅をしたかったのでしょう。
標高の高い地域の直射日光に懲りて、その後は北軽井沢の森を散策しました。木や草が茂り、小川や池もあり、こちらの方が山の上よりずっと涼しかったです。その中でも広大な「野鳥の森」は野生動物のサンクチュアリで、餌付けなどは一切禁止されています。野生動物の生態を観察する研究所でもあります。それで、あちらこちらに定点カメラが設置してあり、スタッフが動物の出没を観察しています。暗くなってから水場にやって来る動物の映像を見せてもらいましたが、入れ替わり立ち代わり様々な動物が現れるので驚きました。ウサギ、キツネ、タヌキ、イノシシ、シカ、そして、クマ。そこは彼らの共同の水場なのです。イノシシは水場の近くの泥の中で泥浴びをして、身体についた虫を取り除くのだそうです。クマは木の幹に爪痕をしっかり残していました。しかし、この森の中はベアドッグもいて、人と野生動物はほとんど接触することがなく、クマが人を襲うこともありません。
木の幹にきれいな円形の巣穴を作ったのはコゲラ(キツツキ)です。幹にはただつついただけの雑な穴も開いていましたが、それはコゲラが木の中にいる虫を獲るときにつけたものだそうです。 この森はブナの木など実のなる木も多く、動物にとっては住みやすい場所なのでしょう。巣箱にもカメラが設置してあり、巣箱でくつろいでいるムササビの姿も見ることができました。
京都府警からは「クマを目撃した」というニュースがよく届きます。山道では、クマよけに鈴を鳴らして歩くことやクマスプレーを持ち歩くことが奨励されていますが、麓の集落にやってきて、民家に押し入って食べ物をあさるというケースもあります。
環境省はクマとのトラブルを避けるため、まずはクマの生態を理解することが大切だと言っています。環境省が出しているリーフレットを読んで、学習したことを簡単に書き記してみます。
①クマの種類
日本のクマは2種類で、北海道にはヒグマ、本州にはツキノワグマが生息しています。したがって、近畿地方に棲むのはツキノワグマです。九州ではすでに絶滅し、四国でもほぼ絶滅に近い状態だそうです。
②クマの餌
クマは冬眠の前の秋に脂肪を蓄積するために体重を増やします。つまり、大量の食料が必要になり、この時期は飽食期と呼ばれます。餌を求めて活動時間が長くなり、ブナやミズナラなどの森の堅果類が不作の場合は行動範囲が拡大し、人間の生活圏にも侵入して、柿や栗などを食べることがあります。人間が育てたおいしい柿や栗の味を覚えたら、またやってくる可能性が高くなります。山菜も好んで食べるので、春に山菜を採りに山に入った人がクマに遭遇するということがよく起こります。
クマは臭覚が鋭く、食べ物を見つける能力も高いようです。また、聴覚も発達していて、音に敏感なので、クマよけの鈴などが役に立つのでしょう。鋭い爪があるため、木登りも得意です。草食がメインですが、たまに捕獲されて放置された鹿の死骸などを食べることがあるそうです。よく知られていることですが、川に上がってくるサケを獲ることもあります。
③冬眠
冬眠は11月下旬から12月に始まり、3月から5月ごろまで続きます。ただし、これは基本情報であって、最近の気候変動で冬眠時期も変わってきているような気がします。メスは冬眠中に出産します。冬眠しながら授乳するという技を持っているのです。子育て期間は1年半ぐらいで、その後は子別れをします。母親と離れた若いクマは出生地を離れ、別の地域に移動します。その時期は分散期と呼ばれますが、オスのクマは生まれて1年半経ったら、自分の知らない場所に行き、自立しなければならないという運命なのですね。この分散期に若いオスが餌を求めて人間の生活圏に出没することが増えるそうです。ちなみに、クマの寿命は大体15歳から20歳です。
④クマに遭遇したらどうするか
もしクマに遭遇してしまったらどうするかについて、環境省は「人身被害」を避けるために取るべき行動をいくつか挙げています。
・遠くにクマを見た場合は人間の存在を鈴などを鳴らして知らせる。人間は落ち着くことが大切。急な動きや大声はクマを驚かせ、その後のクマの行動が読めないので、注意が必要。
・近くにクマを見た場合は落ち着いてクマとの距離を取る。クマは逃げるものを追う習性があるので、慌てず、クマの方を見て静かに話をしながら、ゆっくりあとずさりしてクマから離れる。
・至近距離で突発的に遭遇した場合、クマが攻撃する可能性が高い。被害を最小限に抑えるため、顔や頭を覆い、うつぶせになる。または、クマスプレーをクマの顔に向かって発射する。
基本的にクマも人間には会いたくないし、人間を餌として認識してはいないでしょうが、人体の一部を食べたという事例もあります。クマは学習能力が高く、「猟銃を持った人間以外は自分に危害を加える者はいない」ということを学んだようです。さらに、最近はクマ専門のハンターが使うライフルの性能が高く、かなり離れたところからも狙い撃ちできます。そのため、クマは人間の狙撃の様子を見ることもなく知らないうちに撃たれ、「銃を持った人間は敵」という事実を学ぶ機会を失っているとのことです。
『クマはなぜ人里に出てきたのか』(永幡嘉之)を読んで、学ぶところが多いと感じました。クマはもともと夜行性ですが、昼間里に下りてきて、田んぼのコメや畑のソバを食べるのはメスと幼い子グマです。メスは人間の目をあまり気にしていませんが、ちらちら山の方を見て警戒しているそうです。つまり、山から下りてくるオスを警戒しているのです。オスは繁殖期になると子グマを殺してしまうことがあるからです。人間の敵が人間という場合が多いように、クマの敵もクマなんですね。また、若いクマが単体で農村に現れることがあります。それは、母親のクマが駆除されてしまったため、ひとりで餌を探さなければならず、山に入るとオスのクマに襲われるおそれがあるからです。クマが単体で目撃される場合はたいてい若いクマだそうです。
農村でコメがクマに食べられてしまうなんて、農家にとっては頭が痛い話ですが、実はクマはコメを消化できず、全部糞として出してしまいます。つまり、米からは栄養が吸収できないのです。それを学習したクマは消化の良いソバを食べるようになり、ソバ農家が被害を受けるようになりました。昔は農村では犬が放し飼いにされていて、それが一種の抑止効果を生んでいました。しかし、犬を放し飼いにすることが禁じられてからは、野生動物が犬を警戒する必要がなくなったと言えます。AIの犬を使うというアイデアもありますが、賢いクマはAIが生物ではないし、AIの犬は攻撃しないということをすぐ学んでしまうでしょう。
クマと人間との共存は簡単ではなさそうです。絶滅した、あるいは絶滅が危惧されている地域がある一方、個体が増えている地域もあります。近年は人の居住する地域に出没するクマを「アーバン熊」と呼び、恐怖を煽る記事も見かけます。また、人身被害を引き起こしたクマの駆除について「自然保護に反する」と自治体を糾弾する人々もいます。まるで、極右と極左の対立のようで、どちらも事実を冷静に見る目を失っています。
まだまだ日本には野生生物が生息する山が多いとはいえ、山の開発も進んでいます。木を切って、重機で造成した土地にソーラーパネルを並べると、土の中の種子や生物は生きられません。そこにあった生態系は失われてしまいます。山を開発して人間の生活に利用することが、生態系の破壊につながっているのです。そして、野生動物のための自然の恵みも減少していきます。石炭・石油・原子力ではないクリーンなエネルギーとして注目される太陽光発電ですが、ソーラーパネルが環境破壊をしているというのは皮肉なことですね。風力発電もいろいろな問題が起こっているようですし、どんな発電であっても自然環境を破壊するという方向に進んでいくような気がします。
「野生動物との共存」という表現はほほえましいことばですが、それはファンタジーのようです。犬や猫のような愛玩動物ではないので、野生動物の場合は、人間と野生動物がお互いに交わることなく、敵対することもなく、それぞれが別々に平和に安全に暮らしていくことが大切なのです。どうしたら、現代社会でそれが可能になるのでしょうか。
(なにば 2025年9月23日)
*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)