| 鏡山次郎HP |
 ふるさとの会文章部会 なにば 編
ふるさとの会文章部会 なにば 編
(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会 文章部会 部員)
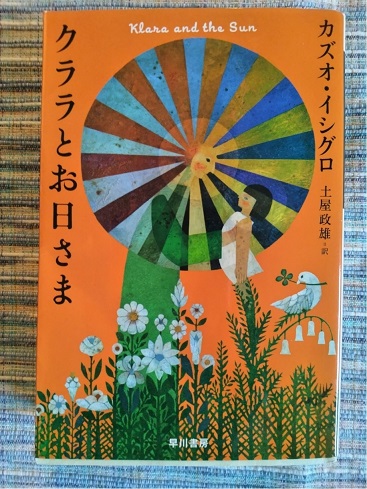
『クララとお日さま』 光と静寂と悲しみ
猛暑の中、体調を崩して、しばらくパンデミックの時のように家にこもり、NETFLIXと読書三昧の日々が続きました。そんな中、カズオ・イシグロの新作『クララとお日さま』を読み返してみました。初版発行は2021年ですが、寡作と言われる作家にとっては最新作です。
この作品の注目点は語り手がAF(Artificial Friend)のクララであるという点です。AFというのは近未来の人型ロボットで、その役割は人間の子どもの忠実な友達になることです。AFは店のショーウインドウや棚に並べられ、子どもとその家族に選ばれるのを待っています。クララはB2型でB3型が登場してからは一つ古い型に当たるAFです。しかし、クララは店長さんに「クララの美質は観察と学習への意欲」と言われ、一目置かれているようなのです。観察者としてのAFの冷静な語り口ではありますが、クララは「わたしの心」「心配」「興奮する」「思う」など感情にまつわる言葉も使うので、読者の私もクララをついつい人間のように見てしまいます。
AFの態度にも人間に似た側面が見て取れます。たとえば、店の中でB3型AFは旧型のAFと距離を置き、自分たちは旧型とは違うということを客に示そうとします。また、購入されて子どもといっしょに外を歩くAFは店の前を通るとき速足になったり、顔をそむけたりします。まるで店に並んでいた過去を否定したいかのようです。ということから、近未来のAFは現時点のAIとは異なり、心に近いものを持っていると言えるでしょう。
ほとんど自己犠牲のように誰かの人生に静かに寄り添って支えながら、観察者として語るという形は『日の名残り』『わたしを離さないで』にも見られましたが、語り手は人間でした。しかし、『クララとお日さま』においては読者はAFの声を聞くことになります。「人間である私がAFに感情移入をするなんて」という抵抗感を抱きつつ、クララの語りに引き込まれてしまいました。
この物語の時代設定は年号が示されていないのではっきりとはわかりませんが、近未来です。この時代には大学以外の物理的な学校が消滅していて、子どもたちは自宅でオブロン端末と呼ばれる機器を使用してオンライン学習をしています。なぜそうなったのかは説明されていませんが、知識の伝達は教室でする必要がないと政府が決めた時代なのでしょう。でも、コミュニケーション能力は外部と接することでしか得られません。ひとつの手段として、近隣の家庭が持ち回りで開くホームパーティーがあり、子どもたちが直に接触する機会を設けています。もうひとつの手段はAFを所有することで、それによって常時友だちとコミュニケーションをとる訓練ができるのです。
しかし、すべての子どもがこのような環境下に置かれているわけではありません。この時代は明確な格差社会であり、裕福な家の子どもだけが「向上処置」を受け、AFを所有し、大学に進めるのです。「向上処置」については詳細が述べられていませんが、どうやら最先端の遺伝子操作技術のようで、それを受けた子どもは優秀な人間になり、大学にも進学できるということらしいのです。ただし、身体に影響を与える「向上処置」には副作用もあり、クララを所有する家庭の少女ジョジーはよく体調不良になり、外出もあまりできません。この辺まで読むと不穏なものを感じます。
家庭が貧しく、「向上処置」を受けていないリックという少年が出てきます。リックはジョジーの家の近くに住み、ジョジーとも仲が良く、クララの目には恋人同士のように見えています。格差社会でも異なった階層の子どもが付き合えるのだということに少しだけ希望の光を感じました。また、「向上処置」を受けていなくても優秀ならば狭き門ではあっても大学に入る可能性はあるようです。カズオ・イシグロはこの時代を完全なディストピアとしては描いていません。
ジョジーとクララの関係は良好で、ジョジーはクララを話し相手として信頼していますし、クララはジョジーのためだけを考えて行動するという姿勢です。クララは太陽エネルギーで生きているためか、お日さまを崇拝しています。お日さまがありとあらゆるものに活力を与えると信じていて、ジョジーが健康になるためにもお日さまの光が必要だと確信しています。AFに太陽への信仰心を持たせることによって、カズオ・イシグロはAFの純粋さを示そうとしているのかもしれません。また、ジョジーの幸いだけを目標とし、そのためなら自分はどうなってもいいという献身ぶりは宮沢賢治の精神世界にも通じるものがあります。
この作品にはよくわからないものがいくつか出てくるのですが、その一つはクララが「クーティングズ・マシン」と呼んでいる機械です。クララにとっては悪の象徴のような機械で、お日さまをさえぎり、不快な音を出し、煙突から黒い煙を吐き出します。工事の作業をする機械のようですが、詳細はわかりません。「クーティングズ」というのは機械の横腹に書かれた会社名なのです。クララにとって倒すべき敵の存在が必要だったのでしょうか。工作機械ですから、何台もあり、1台を破壊してもあまり意味はないのですが、クララにとっては切実な問題だったようです。
ジョジーの家には家政婦のメラニアさんがいます。メラニアさんは移民で片言の英語しか話せません。クララはメラニアさんをいろいろ教えてくれる店長さんのような人だと推測していましたが、メラニアさんはロボットのAFを不気味な存在だと考える、いわば古いタイプの人間だったのです。「ついてくるな、AF。どっかいけ」とクララが怒鳴られる場面もありました。この作品の舞台はどうやらアメリカのようで、この時代も富裕層は移民の家政婦を雇っているのです。
余談ですが、このメラニアという名前が少し気になりました。よくある名前とは言え、トランプの奥さんの名前と同じですね。メラニア夫人はスロベニアからの移民で、英語になまりがあり、それを指摘されることを嫌って、人前であまり話したくないのだと聞いたことがあります。移民大国のアメリカで、大統領夫人ともなると外国人でも英語が完璧でなければならないと考える英語母語話者の人々は心が狭いようにも思います。一方、自分の奥さんが移民であるにも関わらず、移民排斥に向かうトランプにも疑問を抱きます。有色人種の不法移民を乱暴なやり方で強制送還するかたわら、南アフリカから白人の移民を受け入れ、それを大々的に報道させるのを見て、どの地域から来たどんな人種の移民かで差別が生じているような気がします。
話が逸れましたが、その後もクララはジョジーの忠実なAFとして、ジョジーの話に耳を傾けるだけでなく、ジョジーが起き上がれないぐらい体調を崩していたとき、寝ている彼女に十分なお日さまの光が注がれるようにブラインドを開けました。その後、ジョジーの体調は悪化することはなく、峠を越えたという状況に至りました。そして、ジョジーは成長し、やがて大学進学のため、家を出ていきます。
クララの「ジョジーの幸いのために献身する」というミッションは終了しました。最終章ではクララは廃品置き場に置かれています。ある日、そこに店を閉めてしまった店長さんがやって来ます。店長さんは「あなたは、わたしがお世話した最高のAFの一人です」とクララをほめてくれました。クララは店長さんにどうしても伝えたいこととして「お日さまはわたしにとても親切でした」と言います。この場面はとても穏やかなのですが、静謐な悲しみが潜んでいるような気がしました。クララがこの殺風景な廃品置き場で廃棄処分を待っている状態であることがわかるからです。しかし、その悲しみはクララが感じているわけではなく、読者である私が感じたものなのです。それは、悲痛な悲しみではなく、密やかな漠然とした悲しみでもあります。
クララが語る物語を読んで、「諸行無常」「生死一如」「臨終正念」などという仏教の言葉が頭に浮かんできました。クララは絶対的な善として太陽を崇拝しています。IT技術によって造られた無機的なAFでありながら太陽信奉者であり、また、自分の運命を冷静に受け止めているという点でクララは禅僧のような存在でもあります。人間ではないクララのことがこんなに気になるなんて、この作品に作者が仕掛けた網に引っかかってしまったようで、カズオ・イシグロに負けたという気にもなりますが、何度も読み返してみたくなる小説であることは間違いありません。
太陽の光があふれる静かな世界にじわじわと広がる悲しみと不安、まるでシュールレアリズム絵画を見たときのような気分です。タイトルにも記しましたが、「光と静寂と悲しみ」を感じる小説でした。
(なにば 2025年8月26日)
*本サイト掲載の記事、写真等の無断転用をお断りします。(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)