
六兵衛池公園での説明 |
ふるさとの会(ふるさとの良さを活かしたまちづくりを進める会)主催の「第2回ふるさと見学会」は、2008年3月30日(日)、午前10時〜午後2時、26名の参加で「古道 渋谷街道」を訪ねて、歩きました。コースは、六兵衛池公園(10:00)−旧安祥寺川−阿弥陀寺−花山分水路記念碑−花山洞−清閑寺−清水寺(裏門より)−(昼食)−安祥院−現地解散(14:00)でした。
|

六兵衛池公園
|
(1)六兵衛池公園
もともとこの地には、西野村の人たちが共有で使う「総池(そいけ)」と言われる池があったのですが、この池の北側に清水焼で有名な清水六兵衛(きよみずろくべえ)が別荘を構えたために、「六兵衛池」と呼ばれるようになって、地域の人たちから愛されていました。その後、池が埋め立てられて公園になったため、「六兵衛池公園」と呼ばれています。今も公園の北側に水の湧き出るところが残されています。
清水六兵衛(3代)は、幕末・明治期の京焼の陶工で、清水六兵衛家は寛延年間(1748〜1751)に摂津国東五百住村(大阪府)から京都五条坂に移った初代六兵衛以来の陶芸家でした。2代清水六兵衛の次男として京都に生まれ、六兵衛家中興の祖ともいわれています。早くから紅花問屋に奉公に出されたが、長男放蕩のため呼び戻されて家督を相続しました(『朝日日本歴史人物事典』朝日新聞社1994
p563)。
この地に別荘を持った理由は不明ですが、地域の古老の話では、もともとこの地には「東山科村建設」に関わった四手井新五衛・佐太郎親子の家があったということですので、3代目の清水六兵衛がそこから購入したのかも知れません。
|

現在の渋谷街道 |
(2)渋谷街道と旧渋谷街道
渋谷街道は、京都市東山区の馬町からはじまっています。馬町から東へと山を上がり、京都市立東山小学校(旧修道小学校)の前を通り、現在の国道一号線のトンネル(「東山隧道(ずいどう)」)前を横切り北側の旧道を通り、花山洞(かさんどう)を越えると山科・花山に出ます。そして、いくつかの急なカーブを回りながら坂を下り、やがて大石道との交差点(現在の「北花山交差点」)にかかります。その辺りから道も平地になり、旧安祥寺川を越えてすぐの所に、昔の「辻」であった三叉路があります。三叉路を左に曲がれば、「旧渋谷街道」で、厨子奥・御陵・竹鼻をこえて、その道は四ノ宮川西で旧三条街道に合流します。三叉路をまっすぐ進めば、昔は山科本願寺に達したのでしょう。この道が現在の渋谷街道となっています。
京都東山から山科に抜ける渋谷越(しぶたにごえ)は古くは苦集滅道(くずめぢ)とも言われました。名前の由来は、むかし三井寺の開山、教津和尚が三井寺から南山城に行く際にここを通り、その時に木沓(きぐつ)の響きが「苦集滅道(くじゅうめつどう)」の音をしたからとも、また京都から東国に左遷される官吏がこの道を通るときに「苦集滅道」を感じたからだとも言われています(林屋辰三郎『京の道 歴史と民衆』創元社、1974・p65)。また、中世から近世にかけては、山越えの道が大変ぬかるんでいたので「汁谷(しるたに)口」とも呼ばれていました。
|

旧渋谷街道との三叉路 |
(3)旧渋谷街道との三叉路
厨子奥本通りと渋谷街道の交差点にあたる三叉路には、以前「蓮如上人御塚道道標」の一つが建っていました。1969(昭和44)年には写真が撮影されています。『山科の歴史探訪(5)「道標に見る山科」』(山科の歴史を知る会編1994)によりますと、この道標は、1742(寛保2)年に建立されたもので、東側には「寛保二 壬 戌年 三月」、西側には「右 蓮如上人 御塚道」、南側には「右 山しな御坊みち」、そして北側には「是より三丁 京 大阪 江戸 大津 講中」と書かれていました。
その後、自動車が接触し道標が破損したために、現在はありません。ただ、地面にはそれらしき痕跡をみつけることができました。
またI氏によれば、それ以後、交通安全を祈って、同場所南側に地蔵尊が祀られるようになり、これを「安全地蔵」と呼んでいるそうです。
|

現在の旧安祥寺川 |
(4)旧安祥寺川と新八幡田橋(しんやはただきょう)
明治初期までは旧安祥寺川が「安祥寺川」で、音羽川・四ノ宮川と共に山科北部の水を集めて山科川に流れていました。当時の川は、毘沙門堂の西側に源を発し、旧三条街道の北を西に流れて、当麻寺の裏から(御陵)阿弥陀寺の前を通ってこの川に流れ込んでいました。それを明治の後半に工事によって、現在の安祥寺川(旧三条街道の北からまっすぐ南下して、現在のニック・スーパーの西側、安祥寺中学校・山科中央公園の東側、山階小学校の西側を通って、四ノ宮川、音羽川に合流する)が作られ、旧安祥寺川もそれに伴い日ノ岡や御陵地域を流れている小河川の川筋も、旧安祥寺川に流れるように改修されたものです。三叉路交差点から山科乳児保育所・花山児童館の前を通る曲がりくねった細い道は、昔の川の土手で、旧安祥寺川はこの土手に沿って曲がりながら流れていたのです。
|

稚児川が流れ落ちる処 |
また、八幡田橋(しんやはただきょう)から、旧安祥寺川に流れ込んでいる稚児川があります。流れが「ドーンと」落ちていることから、旧安祥寺川との高さが違うのですが、これは改修工事が繰り返されて、旧安祥寺川はかなり低いところを流れるようになったからです。また、「ドーンと、ドーンと」という言葉が「百々(どど)」という言葉の語源になっているということです。
|
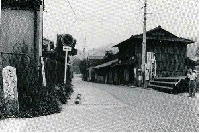
川田道三叉路・道標 |
(5)川田道三叉路・道標(「元慶寺門前道標」)
渋谷街道と川田道との交差点南西角には、昔、道標(宝永二年(1705)の道標)があったことが記録に残っています。
『山科の歴史探訪(3)「山科の歴史を歩く−探訪会資料−」』(山科の歴史を知る会編1989p52)によりますと、「右ハ京ミち」「左今くまの くはんをん 道」「宝永二年 乙 酉 三月日」「沢村道範 建之」と書かれていたということですが、現在は行方不明になっているとのことです。(写真は「山科の歴史探訪(3)p52」より)
|

北花山の愛宕常夜灯 |
(6)北花山・愛宕常夜灯
大石道と渋谷街道との「北花山」交差点から東に50メートルほどの街道の北側に「愛宕常夜燈(あたごじょうやとう)」があります。
愛宕信仰は、京都市右京区の愛宕山山頂にある愛宕神社から発祥した神道の信仰で、京都だけでなく全国にも広まっています。
言い伝えによれば、愛宕神社の神様は、「火伏せ」に霊験のある神として広く信仰されるようになったといいます。古くから修験道の道場であって、愛宕山に集まった修験者によって江戸時代中頃から愛宕信仰が日本全国に広められました。
愛宕山には「千日詣」といって、7 月31
日の夜間に登れば1000回登ったと同じ御利益(ごりやく)があるという話もあります。
山科でもいくつかの所で「愛宕常夜燈」が残っていますが、北花山にあるのも、その一つで、この北花山の常夜燈には表に「愛宕常夜燈」と書かれていて、側面には「昭和十三年六月建之」、裏面には「北花山下之町燈明講中」と書かれています。上部に穴があいているのは、ここに火を灯して夜でも周囲を明るくしたのでしょう。他の地域の昔の写真などを見れば、穴の所に、行燈(あんどん)のように田型の「障子」のようなものがはめ込まれていますから、ここも昔はそうなっていたのだろうと思われます。
「愛宕講」では、「代参講」というものがあり、名簿に書かれた順番に、毎月、代表が愛宕山の愛宕神社にお参りをしたといいます。「講箱」というものがあり、名簿に従って「月番」にあたった家に廻しています。その家は、講の代表としてお参りをすると共に、「愛宕常夜燈」に毎夜燈明をあげることになっていました。
「下之町」という町名は現在の北花山にはありませんが、ただ昔から大石道より西側の山手(現在の「北花山西部」)を「上(かみ)ん町(ちょ)」「中(なか)ん町(ちょ)」、東側(現在の「北花山東部」)を「下(しも)ん町(ちょ)」などと言っていたのを聞いたことがありますから、きっと現在の北花山東部の地域に住んでいた人達が中心となって、この愛宕常夜燈の燈明をあげていたのではないかと思います。
|

北花山・阿弥陀寺 |
(7)花山阿弥陀寺
北花山阿弥陀寺は、正式には「等光山 浄蓮華院 阿弥陀寺」(京都市山科区北花山寺内町9)と称し、本山知恩院の末寺になっています。この阿弥陀寺の創建の詳細は不明ですが、花山にある元慶寺創建の遍照上人と、華山寺創建の愚堂東寔(ぐどうとうしょく)大円宝鑑国師との関係が深いとされています。華山寺の前身は「東山寺」と称し、その阿弥陀堂が現在の阿弥陀寺になったと言われています。
北花山阿弥陀寺の主な寺宝は、「本尊 阿弥陀如来像 一作」「観音菩薩像 一作」「勢至菩薩像 一作」「毘沙門天 一作」で、さまざまな文献によって「本尊阿弥陀如来像は、小松内大臣重盛の念持仏」(『宇治郡名勝志』など)であると言われている。小松内大臣重盛とは、平清盛の子、平重盛のことです。
|
|
(8)花山追分・川の立体交差点
北花山阿弥陀寺・交番署の交差点(「北花山交差点」)を少し西に行った所に、右側に森本酒店(旧本店)、左に北花山公会堂のある三叉路があります。『拾遺名所都図会 北花山』(1787)によれば、この場所は「追分」と記載されています。そして南へ行く道は「勧修寺道」と呼ばれていました。大石街道がまだなかった頃、この三叉路は渋谷街道から勧修寺方面へ向かう大事な分かれ道となっていたのでしょう。
また、そこから少し西に行った道の南側にめずらしい川の立体交差点があります。稚児川が下に流れ、花山分水路が上を流れていまが、いずれも暗渠(あんきょ)になっているため見られません。
|

北花山水路記念碑 |
(9)花山分水路建設と記念碑
「北花山水路」は、琵琶湖山科疏水工事に従事した山科の人たちが、自分たちの田畑にも水を潤したいと、550日の日数と延べ1万5000人をつぎ込んで完成した用水路で、現在も日ノ岡・花山地域を北から南へと流れ、田畑を潤しています。北花山交差点から西へ100m程の道路脇に、北花山水路記念碑が建っています。これは山科西北部各村の農業用水を得るために開通した用水路を記念して、1896(明治29)年に建立されたものです。
「北花山水路紀念碑」によれば、日ノ岡・北花山・上花山・川田・西野山地域の五村に農業用水を得るために、当時建設中だった第一疏水の日ノ岡から分水し、1891年(明治24年)7月から翌年12月にかけての大工事であったと記されています。「以導渓水凡三千間」とありますから、長さは実に約5400mに達すると考えられます。山科にはこの他に、同様の紀念碑が音羽病院北側(音羽分水路記念碑)にあります。
|

花山(稲荷)神社
「一ノ鳥居」跡での説明 |
(10)花山道標と花山稲荷神社「一ノ鳥居」跡
3月9日の福応寺ご住職の講演をきっかけとして、所在不明になっている道標(石碑)が見つかりました。「ふるさと講演会」による思わぬ成果で、最初に設置されていた場所は、『京都の道標』の本によって、北花山市田町89番地の、渋谷街道を東から登ってくる一方通行になっている道と、北花山西ノ野町から上花山に向かう里道との三叉路の南東角にあったということもわかりました。
この道標が置かれていた場所から里道に沿って少し北へ行くと、渋谷街道との交差点にでます。昔は、この交差点の北花山西ノ野町25番地から市田町96番地あたりにかけての所に花山神社の「一の鳥居」が置かれていました。鳥居は赤い木製のもので、京都から渋谷峠を越えてきた参拝者が、この鳥居をくぐって花山(稲荷)神社に参拝したと言います。今でも地元の方から「私たちは鳥居の内側だから、お稲荷さんに守っていただいている」という話も聞きます。北花山西ノ野町25番地の駐車場になっている入口あたりには、今もその礎石が残っています。この鳥居は、残念ながら昭和20年代に車が当たって壊れてしまったので、撤去されたそうです。
|

稚児川のダム |
(11)稚児(ちご)川の決壊
稚児川は、花山山の西側(現在の東山ドライブウェー道路沿い)の上稚児ケ池・下稚児ケ池から、山の中を南側に流れ、国道一号線東山トンネルの山科側出口の北側の谷から東方向に向かい谷沿いに流れ、阿弥陀寺の墓地の横を通って、現在の北花山公会堂の少し西側附近で渋谷街道を横切り、そこから東方向に一直線に流れ、旧安祥寺川に流れ込んでいます。地元の年配の人の話では、戦前から戦中にかけては、子どもたちが稚児ケ池で泳いだり、魚釣りを楽しんだりもしたといいます。また、大雨の時は、稚児川が渋谷街道と交差する一帯から下流は、洪水や河川の氾濫で水につかることもあったということです。
花山地域は山麓に位置するため、水利の問題は深刻で、稚児川は、まさに花山地域の人々にとっては「生命線」でした。
1935(昭和10)年8月10日には、稚児ヶ池(当時は、北花山地域上流にもいくつかの溜池やダムが設けられていた)決壊による土石流で、稚児川が氾濫し、北花山で死者が出るなど北花山・厨子奥地域に大きな被害が出ました。地域の古老は次のように話しています。
「稚児ヶ池の決壊というのは、なんか花山の辺は全部飲まれはったんです。花山天文台に勤めたはった人のお嬢ちゃんが巻き込まれてしまはったとか、魚屋をしたはったおじちゃんが、飲まれはったとか聞きました。当時、花山から厨子奥へ行く渋谷道は土手でしたんよ。で、(道の)両端がドーンと落ちていますねん。それで、もう川田道になってるけど、あのへんザーッと流れ込んだとか、酒屋さんの母屋はんの、さらに上の方の家に、ごっつい丸太が貫いたとかね。そんな話を聞いていました。厨子奥の方はあまり被害を聞かなかったようです。水はつかはったやろうけど・・・」
|

花山洞 |
(12)渋谷街道改修工事と花山洞
京都洛中との交流の道である渋谷街道は、花山・山科地域の人々にとって重要な道であったため、その改修工事も度々行われています。そのもっとも顕著な例が1811(文化8)年に行われた大規模な道路改修工事で、渋谷街道はそれまで岩角が多く、通行や牛馬の往来が難儀で、とくに雨天後にはけが人も多かったといいます。工事は、郷民からの工費徴収をもとに、岩場を削り取り、小石・土砂によって道幅を広げ、あわせて下水掘をも作るという本格的なものでした。
|

花山洞の前での説明 |
続いて大きな工事は、1903(明治36)年4月28日に完成した「渋谷隧道(ずいどう)」(花山洞)でした。この渋谷隧道は、現在国道一号線五条坂トンネルの北側に平行して現存し、通行も可能です。この渋谷峠は「汁谷」とも書かれたように、水はけが悪く交通の難所で、そこで1899(明治32)年2月18日改修計画が京都府会に出され、翌年12月に予算化することが可決されました。工事は1902(明治35)年4月3日に始まり、翌年の4月28日に完成しました。工事を請け負ったのは岡崎の「大西土木」という会社で、京都日出新聞(1903年5月20日)によれば、「この隧道は、(従来の峠から)三四尺余り地下へ切り下げ、隧道内に水の落下を防ぐために亜鉛(トタン)屋根をふいた。隧道の花山側入口上部には「火山洞」という三文字が掲げられた」とあります。新聞によればこの額は「火山洞」ですが、現地へ行ってみれば「花山洞」となっています。新聞の間違いか、後に作り替えられたのかは不明です。おそらく当初から「花山洞」になっていたのではないでしょうか。また、渋谷街道は、後年の1923(大正2)年にも大規模な道路改修工事が行われています。
|

清閑寺門前での記念撮影 |
(13)清閑寺と六条・高倉天皇御陵
清閑寺(せいかんじ)は「歌の中山清閑寺」で有名で、真言宗智山派に属しています。802(延暦21)年に紹継法師によって創建されたと伝えられている寺です。昔は寺域も広く、法華三昧(ほっけざんまい)堂や宝塔などが広く東山一帯に展開していたそうですが、応仁の乱ですべて焼けてしまって、今は菅原道真の作と言われる本尊十一面観音像を安置する本堂を持っているだけとなっています。
昔から「京の花見の名所」として知られ、春には多くの人が清閑寺に訪れたそうです。庭には、「要石(かなめいし)」があり、そこに立てば京都の街があたかも扇を開いたかのように展望できます。またこの石に願をかけると願いがかなうと言われています。
清閑寺の近くには、六条天皇・高倉天皇の御陵と小督局(こごおのつぼね)の墓があります。これは『平家物語』に出てくる話で、ヒロイン小督局が平清盛に追われて清閑寺に逃げてきた時、寵愛する高倉天皇が「私が死んだら、局のいる清閑寺へ葬ってほしい」との遺言をしたので、この地に埋葬されることになったということです。
ちなみに山号の「歌の中山」は、この清閑寺から清水寺までの山道のことを指しています。
|

清水寺境内での説明 |
(14)清水寺と坂上田村麻呂
清水寺については、あまりにも有名なので詳細は述べる必要はないと思いますが、その由緒(縁起)が余りにも山科・音羽山の「牛尾山法厳寺(牛尾観音)」と酷似しています。法厳寺は「清水寺の元寺」であると言われています。
縁起では、奈良時代の末期(778)に奈良の小島寺の延鎮(えんちん)が夢告によりこの地に来て行叡(ぎょうえい)に逢い、その遺命により千手観音を彫り奉納して開山したというものです。
その後坂上田村麻呂が妻の安産のために鹿狩りをしてこの地に来て、殺生を延鎮に諭され、観音に帰依して清水寺を造ったというものです。はじめは「北観音寺」と言われていましたが、音羽の滝にちなんで「清水寺」と名を改めたということです。
|

安祥院境内の
木食養阿上人供養塔・入定地 |
(15)木食養阿上人と安祥院(あんしょういん)
清水寺から坂を五条通に向かって下がった所に、安祥院(あんしょういん)があります。
東山木食寺安祥院(とうざんもくじきでらあんしょういん)は、山科・日ノ岡で旧東海道の修復に努力し、車石や「南無阿弥陀仏」の六字名号碑を設置した木食養阿上人が建立した寺で、上人が即身仏(そくしんぶつ)として入定(にゅうじょう)した地でもあります。
寺には、日ノ岡の車石の他、木食上人が使っていた編笠や杖などが残されており、木食上人の墳墓の石室には「即身仏(ミイラ)」となった上人が今なお結跏趺坐(けっかふざ)していると伝えられています。
お寺の境内西側にある「日限地蔵」は、日を限って願い事をすると開運・厄除け・安産などがかなうと伝えられ人気を集めています。寺には木食上人に関する貴重な文書資料も残されています。
(終わり) 2008年4月21日 鏡山次郎記 |
![]() 第6回 古道 渋谷街道を訪ねて
第6回 古道 渋谷街道を訪ねて![]()